|
スズネの信じられないという顔と声がの心を挫きにきていた。
いや、もしかしたらうまく聞き取れなかったか聞き間違えたのが原因かもしれない。
そう思い、恐る恐る再度思ったことを伝える。
「だ、だから…白馬の、王子様…」 「白馬の王子ぃ?アラタが?」 すると次の瞬間、スズネは我慢ならないと言わんばかりに腹を抱えて笑い出した。 夕食のために集まっていた他の生徒達の何人かが不思議そうにスズネを見つめる。 「何で笑うの!」 「何でって、だって、分かって言ってるんか? アラタやで、あのアラタを白馬の王子って、そりゃ、笑うしかあらへんやん!」 そう言って笑いを止めるどころか更に大声で笑い出す。 笑いすぎて苦しいのか、目に涙すら浮かべている。 泣きたいのはこっちだ。そこまで笑わなくてもいいじゃないか。 唇を噛んで泣きたくなるのに耐えていると、見かねて二人の様子を窺っていたカゲトラとタケルが食事の手を止め、口を開いた。 「スズネ、その辺にしておけ」 「そうだよ。アラタくんに酷いよ」 「じゃあ二人はアラタが白馬の王子にぴったりだと思うんか?」 咎めていた二人も、スズネの言葉に視線を彷徨わせ始めた。 そんな二人を見てが落胆の表情を浮かべるのに対し、スズネはにやにやとした先程とはまた別の笑みを浮かべる。 二人ともスズネと同意見なのだろう。 あのアラタが白馬の王子などどう考えても似合わないと思っているのだ。 「まあ、アラタくんは王子様って感じとはちょっと違うかもしれないけど…」 「そうだとしても、には白馬の王子に見えたんだろ。にとって王子には違いない」 「仮に王子としても、アラタなら白馬にのるっちゅーよりも、白馬をのり捨てて行く王子やろうけどな。馬にのらずに自分で走りそうや」 「もう!スズネってばさっきからいい加減にしてよ!!」 あれはつい昨日のことだ。 がダック壮の階段で足を踏み外し、転げ落ちそうになったところをアラタが咄嗟に抱き留めてくれた。 言ってしまえばそれだけのことであり、普段周りからとろいだののろいだのと 言われ続けているには誰かにこうして助けてもらうなど日常茶飯事のことだった。 だというのに、にはあの瞬間、確かにアラタは白馬の王子に見えたのだ。 それこそカゲトラやタケルといった同じ第1小隊の仲間やハーネスのメンバーに助けられても そんなふうに思ったことはない。なのにアラタにはそう思えた。 にはそれが不思議で、だからスズネ達に話したのに、こうして笑われる事態となってしまっている。 それがとしては非常に納得がいかない。 「白馬の王子様って言ったら白馬の王子様だったんだもの…っ」 「ふーん、なら、確認してみよか?」 「確認?」 「そうや。暫くアラタの行動を監視してみて、本当に王子か確認するってわけや」 「監視って…アラタくんを監視とかスズネってば何を考えてるんだよ」 「別にええやろ。ちょーっと、様子を見るだけ。 アラタがの言う通り、王子に見える時があるかどうか」 そんなことをしても無駄だろうけど。スズネの言葉にはそういう意味合いが含まれていた。 スカートの端をぎゅっと握りしめ、考える。 アラタを監視するなどアラタに失礼な行為だ。 しかし、このままではスズネに信じてもらえず、馬鹿にされたままということになる。 自分の考えをこうして否定されるのも、アラタを馬鹿にされたままでいるのも、どちらも嫌だ。 スズネを見返したい。白馬の王子に見えるのだと思わせたい。 「……分かった。アラタくんには悪いけど、それ、やろう!」 「お、おい、、スズネのこんな馬鹿げた提案なんてのらない方が…」 「カゲトラは黙っとき。よし、早速明日から監視開始や!」 「うん!」 きっと監視していればアラタが王子に見える瞬間が一度でもある筈だ。 そう思い、は力強く頷く。 カゲトラとタケルが心配そうな表情を浮かべていたが見なかったことにした。 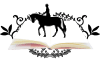 「あっ、アラタくんだ」 日が変わり、次の日の朝。 朝食をとっていると、食堂へとアラタがやって来た。 欠伸をしていることから、まだ眠気がさめていないのであろうことがよく分かる。 ごくり、と生唾を飲み込みアラタの様子を窺う。 こちらが見ていることに気が付かないアラタは食事を受け取り、 既に食事を始めているジェノック第1小隊の所へ向かい、彼らに遅れて食事を始めた。 「あれのどこが王子の食べ方やねん」 様子を窺っていると、アラタはヒカルの朝食のおかずを勝手に奪って食べようとしていた。 それに食べ方も所謂王子の気品ある食べ方とは程遠い。 それこそおかずを奪われそうになったヒカルの方がよっぽどか王子らしさが漂っている。 スズネの表情に呆れの色が浮かぶ。 早くもプラスどころかマイナス方面へと働いたアラタの行動に、の心は挫かれざるを得なかった。 朝食を終え、登校する際も監視をするためにジェノック第1小隊に それを隠しながら一緒に登校しようと持ち掛ければ、特に断る理由もないためかあっさりと了承を得られた。 だが、そうなることになったのは良いのだが 気が付けばアラタの寝坊の話で持ち切りになっている。 ヒカルとサクヤに咎められ、ハルキとカゲトラには呆れられ、タケルには苦笑されるという状況だ。 無論、その話題でスズネがアラタのことを王子と思うわけもない。 先程同様呆れたという表情であり、これではスズネを見返すことはできない。 (でも、まだまだ今日は始まったばかり… 今日は午後からハーネスとジェノックの合同授業があるし、授業中のアラタくんを見ていられる) 見返せる要素を特に見つけられぬまま学園に到着し、いくつかの授業を終え(尚、昼食では朝食と変わらない様子だったためスズネには更に呆れられることとなった)、 午後の合同授業が始まった。 今度こそとはアラタのことを信じ授業へと臨んだ。 しかし、やはりと言うべきかの願いは外れることとなった。 「、見てみ」 授業も半ばまで進み、に眠気が襲い始めてきた頃。 スズネが小声で声をかけてきた。きっとアラタのことだろうとは彼を見つめる。 アラタはうつらうつらとしており、少しするとぱたりと机に俯せになった。 明らかにあの様子は眠っている。きっとそのうち先生が怒声を飛ばすに違いない。 「今日一日監視するつもりやったけど、正直これ以上監視しても無駄やな。 これでも分かったやろ。アラタは王子なんかやないって」 スズネはアラタから視線を外し、黒板へとそれを向ける。 言葉通り、アラタの監視を止めるつもりなのだ。 まだ続けよう、と言いたかった。王子なのだからと。 しかしそれがにはできなかった。 残念ながらスズネの言う通りなのでは、という思いが芽生え始めていた。 他の皆が同じことをしても見えなかったのにアラタだけがそう見えたというのは中々おかしな話だ。 だからあれは勘違いだったのかもしれない。 そうだとすれば説明がつく。こんなにもアラタは白馬の王子とは程遠いのだから。 ついも呆れた顔で溜息を吐く。 なんとも幸せそうな顔で居眠りを続けるアラタを見て、 としてもそうならずにはいられなかった。 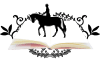 結局アラタの監視は止め、そのまま時間は経ち時刻は夕方となっていた。 はとぼとぼと帰り道を一人歩く。 学園では現在ウォータイムが行われているが、今日のミッションにはの所属するハーネス第1小隊は外されており出番はない。 カゲトラ達は残ってバトルの様子を見ていくと言ったが、にはそんな気分にはなれなかった。 そのため、こうして一人でダック壮への帰り道を歩いている。 歩きながら、周りが見えないほど頭の中はアラタのことでいっぱいだった。 アラタは白馬の王子では本当にないのだろうか。あんなにもそう見えたのに。 しかし、あの様子を見る限りあまりにも違いすぎる。 この矛盾がを悩ませ、もやもやとした気分にさせる。周りへの集中力に欠いていた。 「危ないっ!!」 突然とそんな声が聞こえたかと思えば、腕を引かれ、ほんの少しの肩と足への痛み。 一体、何が起こったのだろうか。 訳が分からず、目を瞬かせれば知らぬ間に地面に転がっていた。 今の今まで立って歩いていたというのにどういうことなのか分からない。 そして、目の前には見知った顔が自分の肩を抱き、自分と同じように地面に転がっているではないか。 「大丈夫か?」 「アラタくん…?」 の様子を確認したアラタは安心したように息を吐き、上半身を起こす。 それに倣いも上半身を起こし、何が起こったのかを理解しようとした。 倒れているとアラタのすぐ横には自転車と、それに乗った心配そうな顔をした男性がいた。 それに周りの人達が男性同様に心配そうな顔でこちらを見つめている。 「き、君達、大丈夫か!?」 「おう、俺なら平気だぜ」 「あ…わ、私も…」 男性が声をかけてきたため、まだ混乱しているもののアラタと共に無事を伝える。 すると男性の顔は安心した表情へと変わり、 気をつけろよ等と言って自転車を漕いで走り去って行った。 その姿を見つめながら混乱した頭を整理していく。倒れていた自分達と心配してきた自転車の男性。 答えは簡単だ。 つまりは、あの自転車に轢かれそうになったところをアラタが助けてくれたらしい。 「ってば全然前を見てなかっただろ。危ないだろ、気を付けろよ」 「ごめん……あ、あと、ありがとう」 漸く状況を理解して礼を言えば、いいって、とアラタは眩しいばかりの笑顔で笑った。 その笑顔にどきりとするも、一昨日のように白馬の王子には見えない。 やはりあれは勘違いだったのだろうか。スズネの言う通りなのだろうか。 そんなの思いなど露知らずアラタは立ち上がり、手を差し伸べてきた。 この手に掴まって立ち上がれということなのだろう。 その好意を素直に受け取り、手を取っても立ち上がる。 だが、立ち上がった際に足にずきりとした痛みが走り、思わず顔を少し歪めた。 どうやら先程ので足を少し痛めたらしい。 アラタが庇ってくれなければこれだけでは済まなかったかもしれないことを考えれば、 大した怪我ではないのかもしれないが。 「足、痛いのか?」 「ちょっとだけ。でも、歩けないことはなさそうだし大丈夫だよ」 この程度の痛みならば、明日にはもう治っているだろう。 所詮はあんなことがあった直後だからの痛みにすぎない。 しかしアラタは腕を組み、うんうんと唸り始める。 首を傾げてそんな様子を見つめていれば、何か閃いたのか唸るのを止め、しゃがみこみ背を見せてきた。 「ほら」 「アラタくん?」 「大丈夫って言ってもそれじゃあ辛いだろ。ダック壮までおぶっていくよ」 「えっ、大丈夫だから! そんなことしなくても…」 「いいから、ほら、乗れって」 大したことはないのにおぶってもらうなどアラタに悪い。 それに、何よりも恥ずかしい。だが何かと理由をつけて断ってもアラタがそれで引くとは思えない。 おぶられることを渋っていれば、アラタは早くと急かし、 周りの視線も集まってきていたたまれない気持ちになっていく。 仕方なくは意を決し、アラタの背へと弱弱しくしがみつく。 とはいえ恥ずかしさを隠すために勢いは良かったため、アラタが少しばかり前のめりになってしまったが、 なんとかバランスを取り戻したようだった。 「よし、じゃあ行くぞ」 そう言ってアラタは立ち上がり、歩き出す。 は周りの視線が案の定気になって仕方がなく、それから避けるように目を瞑る。 それに加え、アラタの身体の温かさに胸がどきどきして煩い。 年頃の男の子というのもあり、意外にもアラタの身体はしっかりとしている。 女であるとは違う。ああこれが男の子なんだなと意識させられる。 また、胸が高鳴るのはそれだけでもないようだった。 じわりと胸に広がる感覚があった。それは、前に感じたあの感覚だった。 否定されかけていた感覚が戻ってくる。 「…………やっぱり、王子様だ」 「王子様?」 「う、ううん、何でもない。……何でも、ないの」 アラタはの言葉に、ならいいけど、と答え周りの視線など気にせず をおぶりダック壮へと向かう。 そんなアラタの背に、は今度はしっかりとしがみつく。 確かに、スズネの言う通りアラタは白馬の王子とは程遠いのかもしれない。 それでも、にとってはアラタは誰よりもそれに相応しい人間に見えた。 白馬にのらない王子様 |